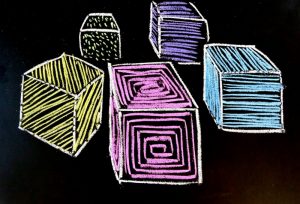人間は球体である--阿川佐和子に学ぶ「聞く力」
ベストセラー『聞く力』とアマゾンレビュー
阿川佐和子さん(作家・エッセイスト)のベストセラー『聞く力 心をひらく35のヒント』(文春新書)を再読しました。この本は2012年のベストセラー1位。2013年秋の時点で発行部数150万部に到達しています。当時わたしも読んでみて、とても面白かった記憶がありますが、今回あらためてページをめくってみました。

感想は…やっぱり面白い! 900回以上重ねたインタビューから選りすぐったエピソードが面白い。北野武、デーモン小暮、柳家小さん…このブログ記事で短く引用するだけでは到底伝わらなさそうな、それぞれのひとの断面がスケッチされています。
ところが読み終わった後、アマゾンのレビューを見てみると、これがビックリするぐらい酷評の嵐。上位のレビューは軒並み低評価が並んでいます。典型的な意見は「『聞く力』というから実践的な技術が書かれている本、自己啓発書かとおもったら、ただのエッセイ、体験談じゃないか」という不満でした。まあそう意味では、むりやり自己啓発書の体裁にしたけれど、中身はエッセイといえるかもしれません。
そんな賛否両論のベストセラー『聞く力』から、わたしが「役に立った」と思ったことを少しだけご紹介します。
「質問は一つだけ用意しなさい」
「インタビューするときは、質問を一つだけ用意して、出かけなさい」
これ実は、阿川さん自身の言葉ではありません。阿川さんの先輩アナウンサーの本にあった項目だそうです。インタビューを一度でも経験したひとなら、質問を1つしか用意しないなんて、これは荒唐無稽な話だとおもうに違いありません。
ところがその先輩は、こういう解説を加えていました。
「もし一つしか質問を用意していなかったら、当然、次の質問をその場で考えなければならない。次の質問を見つけるためのヒントはどこに隠れているだろう。隠れているとすれば、一つ目の質問に答えている相手の、答えのなかである。そうなれば、質問者は本気で相手の話を聞かざるを得ない。そして、本気で相手の話を聞けば、必ずその答えのなかから、次の質問が見つかるはずである」
阿川さんはその解説を読んで「目から鱗の驚き」を覚えます。
そうか…。まさに目から鱗の驚きでした。質問をする。答えが返ってくる。その答えのなかの何かに疑問を盛って、次の質問をする。また答えが返ってくる。その答えを聞いて、次の質問をする。まさにチェーンのようなやりとりを続けてインタビューを進めていくことが大事なのだと教えられたのです。
それまでは20項目の質問をシミュレーション質問をレポート用紙に書き留めてからインタビューに臨んでいた阿川さんは、徐々に、徐々に質問項目を減らしていって、メモ用紙も作らないようになって、今ではだいたい頭のなかに「三本ぐらいの柱」を立てるようにしているのだそうです。
用意したたくさんの質問を順番にこなすことにとらわれると、どうしても掘り下げが表面的な部分にとどまってしまいがちです。わたし自身、ひとつの質問の回答を聴きながら、それは半分上の空で、頭の中は次に用意した質問のことを考えているなんてこともよくあるので、「質問はひとつ」あるいは「三本の柱」の話は、とても印象的でした。

人間は三百六十度の球体である
その「質問はひとつ」「三本の柱」と合わせて興味を引かれたのが、こんな喩えです。
人は皆、三百六十度の球体で、それぞれの角度に異なる性格を持っていて、相手によってその都度、向ける角度を調節しているのではないか。(中略)いつまで経っても未知の部分があるからこそ、その人に対する興味が尽きることがないのだと思います。

「球体」である人間の未知の部分を、好奇心と質問によって浮かびあがらせる、そこがまたインタビューの醍醐味なのかもしれません。自分にとって苦手な人も「三百六十度の球体」だとイメージすると、今はまだ見えていない横側、斜め側、裏側がどうなっているのか、俄然、気になってきませんか?
※この記事は旧ブログ「質問学」(2015-10-18)の転載です